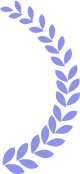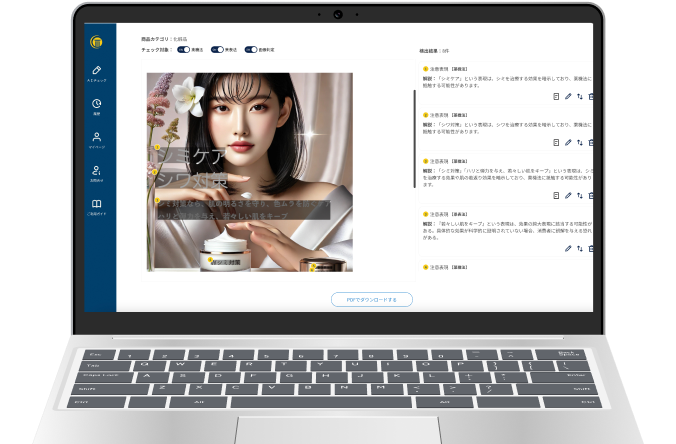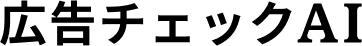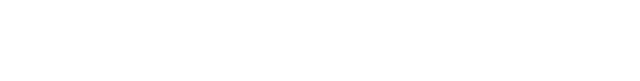BLOG
【2025年】医療広告ガイドラインの主要な改訂ポイントを解説!
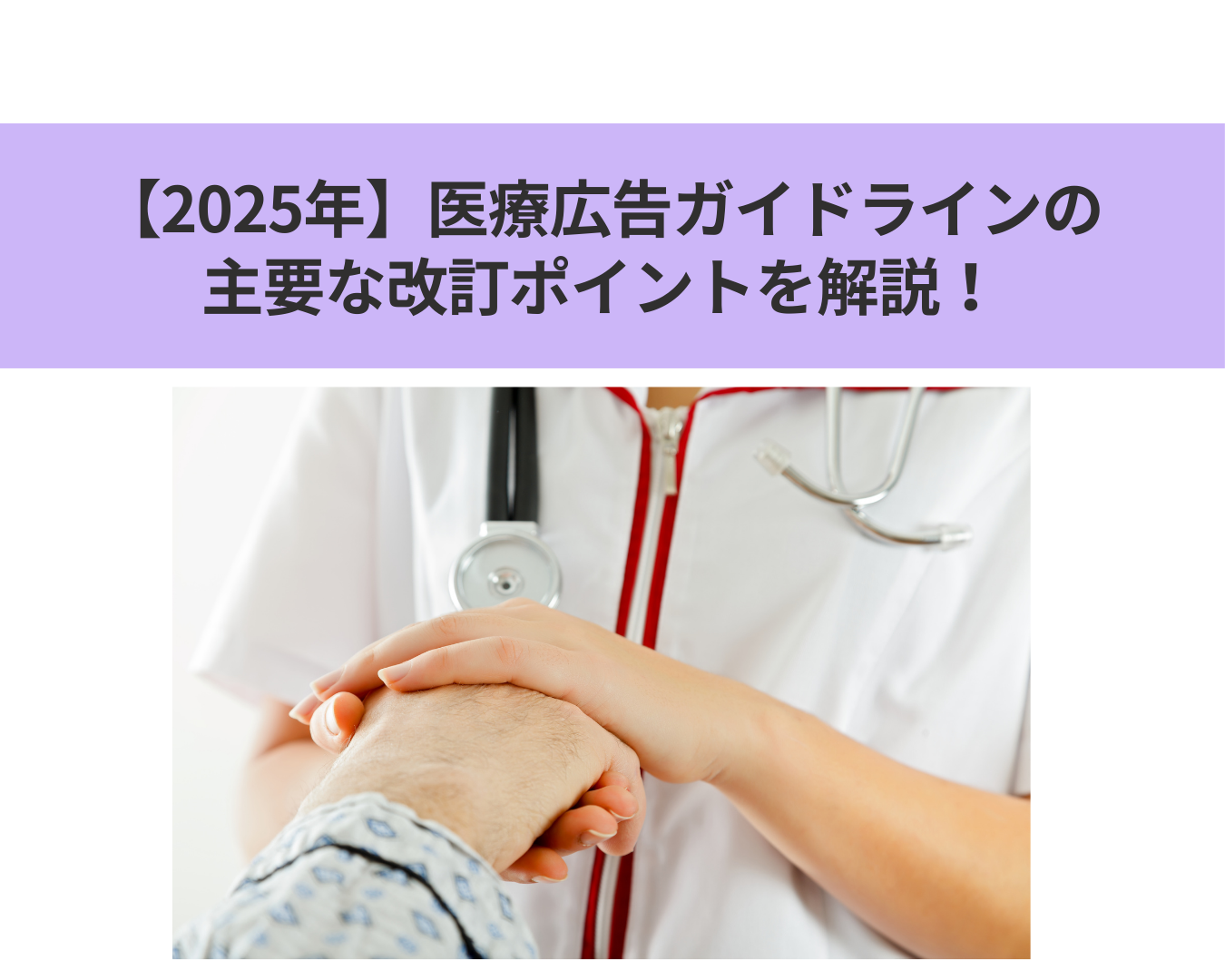
近年、SNSや動画プラットフォームを利用した情報発信が活発になる一方で、医療広告における不適切な表示や誇大な表現が問題視されてきました。こうした状況を受け、患者さんがより安全で正確な医療情報を得られるよう、2025年3月に医療広告ガイドラインが改訂されました。
今回の改訂では、特にSNSや動画広告、そして自由診療に関する広告のルールが具体的に整備され、医療機関や広告担当者にとって注意すべき点が多く盛り込まれています。この記事では、主要な変更点を分かりやすく解説いたします。
今回の医療広告ガイドライン改訂で押さえておくべき主要ポイント
今回のガイドライン改訂で、特に注目すべきは以下のポイントです。
SNS広告:プロフィールからハッシュタグ(#)まで規制対象に
今回の改訂で、SNSにおける医療広告の範囲や求められる表示形態がより明確になりました。
・広告と見なされる範囲の明記
医療機関への誘引を目的とするSNSのプロフィール情報、テキスト・画像・動画などの投稿内容(一定期間で限定公開されるものも含む)、そして返信内容も広告と見なされます。また、投稿や返信内のタグ付け部分も広告に相当すると明記されました。
・不適切なハッシュタグの使用禁止
投稿内容と直接関係のない人気ハッシュタグ(例:「#美容」「#ダイエット」などトレンド性の高いもの)を使い、閲覧数を増やそうとする行為は不適切と明記されました。
・SNSでの適切な情報表示の形態を明確化
例えば自由診療に関する情報をSNSで発信する際は、投稿内もしくは返信コメントのどこかで必ず「標準的な費用、治療期間、回数」「主なリスクや副作用」を示す必要がありますが、患者さんが分かりやすいよう、「一体的かつ一覧性」をもって示す必要があると明記されました。返信等を用いて情報を細切れに投稿したり、単に外部リンクに情報を掲載したりするだけでは不十分です。
動画広告:情報表示の「一体性・一覧性」がより厳格に
動画プラットフォームを利用した広告にも、新たな基準が設けられました。
・情報の一体性と一覧性の強化
治療内容、費用、副作用など、患者さんが必要とする情報は、動画の本編や概要欄などに一体性かつ一覧性をもって表示されている必要があることが明記されました。「詳細は概要欄へ」といった形で情報が分散している場合は規制違反となる可能性があります。
・治療内容または効果に関する体験談の表現の禁止
患者さん自身や家族等からの伝聞に基づいた主体的な体験談を表示して医療機関へ誘引することは従来から禁止されていましたが、今回の改訂では動画内での音声や映像であっても、治療内容や効果に関する体験談を紹介することは違反であると明記されました。
再生医療関連の広告:科学的根拠の乏しい誇大広告を明示し規制をより強化
再生医療関連の広告を中心に、患者さんに誤認を与える広告表示の具体例が示されました。
・再生医療に関する誇大広告の禁止
自由診療で行われる「再生医療」が標準治療と同等もしくはそれ以上の有効性や安全性をもつかのような表現は誇大広告であることが明記されました。具体的な例として、エクソソームや培養上清液については規制当局等で有効性・安全性が十分に確認されておらず、医療技術として科学的な根拠が乏しいことが今回の改訂で追加されました。
・「再生医療等提供計画」について誤認を与えさせる表示の禁止
再生医療等提供施設として認定を受けている旨の表示は、厚生労働省等による特別な承認・認可・お墨付きを得ていると誤認を与える表示であり誇大広告にあたります。あくまで再生医療等提供計画を届出済みである、もしくは計画番号を記載する程度の表現にとどめる必要があると明記されました。
虚偽広告・比較優良広告・根拠のない最大級表現などへの規制は引き続き遵守!
従来からある、患者さんに誤認を与える可能性のある広告表現への規制についても引き続き注意が必要です。
例えば、以下のような表現に注意しましょう。
・虚偽広告:「絶対安全」「副作用がなく安心」など事実と異なる虚偽の表示
・比較優良広告:「日本一の病院」「他院よりも安い」など、他の医療機関と比較して費用や治療効果の優位性を示す表示
・根拠のない最大級表現:「最先端の治療」「最適な医療」などの科学的根拠の乏しい最大級表示
(参考文献)
・厚生労働省 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)
さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もお読みください。
▶関連記事:クリニックの広告で守るべき医療広告ガイドラインとは?違反事例も紹介
医療機関・広告担当者が今すぐ取り組むべきこと
これらの変更点を踏まえ、医療機関および広告制作に携わる皆様は、以下の対応を行う必要があるでしょう。
SNSや動画制作時の表示ルールを徹底すること
SNSや動画では情報を一体性・一覧性に表示できるよう制作段階できちんと構成案を作り込む必要があります。特に治療メリットの紹介や治療前後の写真を掲載する場合には、治療のリスクや副作用、費用、治療期間など併せて記載すべき項目を整理し、患者さんに明確に伝わるように一覧で表示しましょう。
最新情報を確認した上で広告制作を行うこと
医療広告ガイドラインは、必ずしも毎年改訂されるわけではないものの、近年では年に複数回の改訂や、関連資料の更新など頻繁な改訂が見られます。医療広告の制作時にはその都度、最新のガイドライン及び関連通知を確認することが重要です。
定期的な社内教育を行うこと
情報発信に関わる全てのスタッフが新しい規制内容を正しく理解し、遵守するための研修や情報共有を社内で徹底しましょう。
ガイドラインを遵守し、適切な医療広告を制作しよう!
2025年に改定された医療広告ガイドラインでは、患者さんへ正しい情報をより分かりやすく伝えることが一層重視されるようになりました。特にSNSや動画広告においては、情報が整理され全体像を把握しやすく発信すること、そしてエビデンスに基づいた情報提供を徹底することが求められています。
ただ、医療広告ガイドラインは近年頻繁に改訂されており、常に最新の情報を把握し、的確に対応していくことに難しさを感じている広告担当者の方も多いのではないでしょうか。
そのような状況でお役に立てるのが、Archaicの広告チェックAIです。
広告チェックAIは、最新の医療広告ガイドラインに沿って広告文のチェックをフォローし、問題のある表現にはより適切な言い換えをご提案します。動画や画像のチェックにも対応していますので、広告制作の効率化やコンプライアンスについてお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
AIを搭載した広告表現チェックツールにURLや画像を入力するだけで、
法令
(薬機法、景表法など)
に抵触しているかどうかを瞬時に確認し、
言い換え文章を出力。
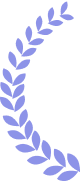
初期費用
0
円
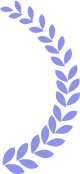
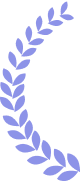
チェック工数
9
割削減
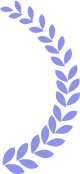
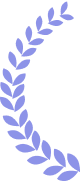
お客様のご要望に応じた
カスタマイズ開発が
対応可能