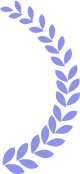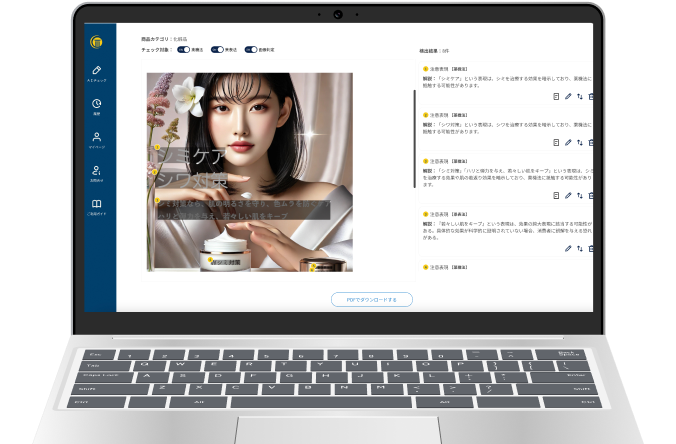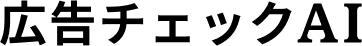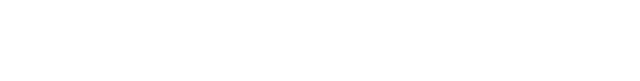BLOG
化粧品成分の特記表示ルールが40年ぶりに刷新!広告・薬事担当者に求められる対応とは
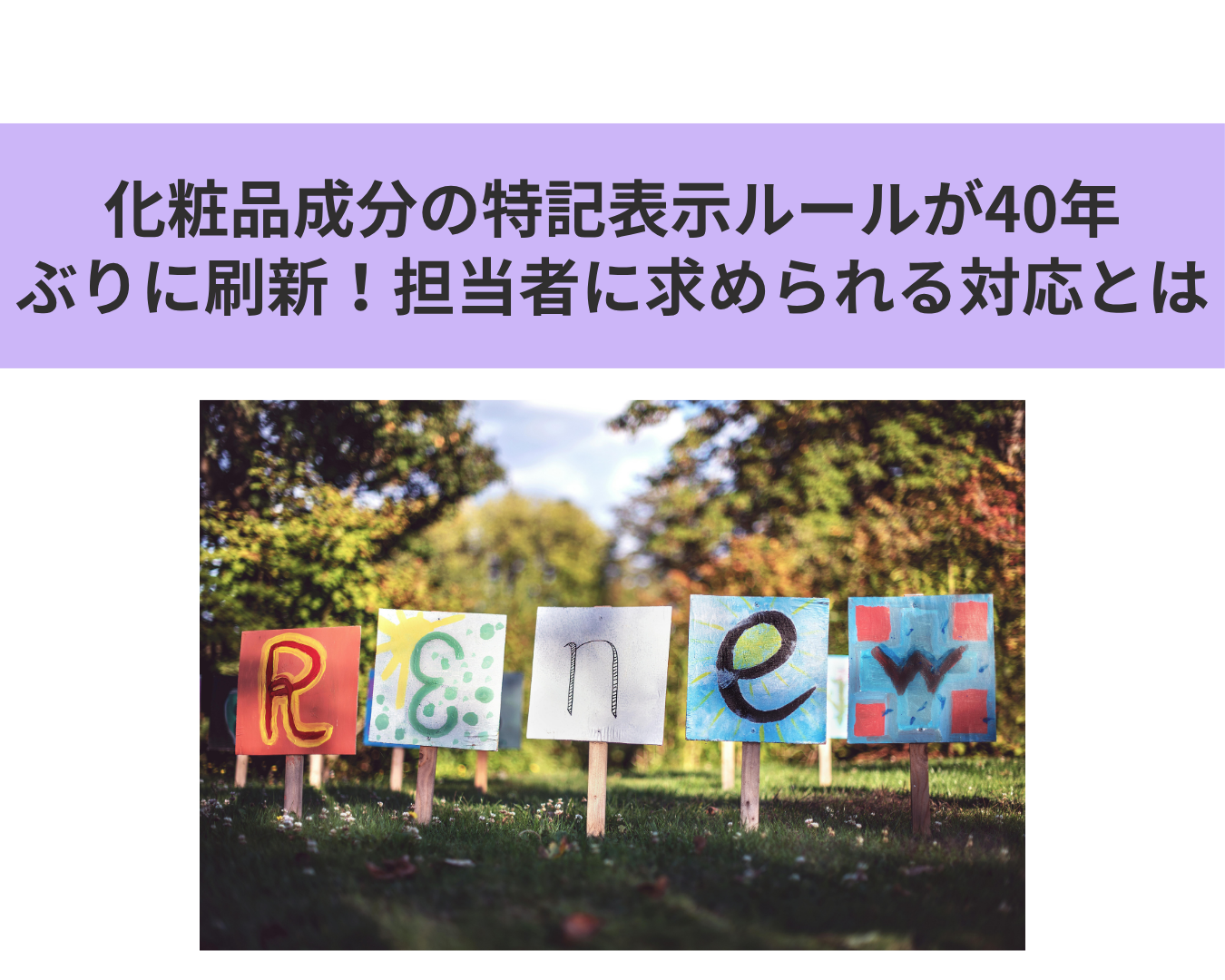
2025年3月10日、厚生労働省は化粧品の特定成分表示に関するルールを約40年ぶりに刷新しました。新たな通知(医薬監麻発0310第3号)により1985年の旧通知(薬監53号)は廃止され、特定の成分を表示する際の要件が強化されています。
今回の改正は、SNSや動画広告をはじめとする多様なメディアが普及した現代の状況を踏まえ、消費者の誤解を防ぎ、より理解しやすい情報提供を促すことを目的としています。
この記事では、企業の広告・薬事担当者の皆様に向けて、今回のルール改正のポイントと、今後求められる対応を解説します。
そもそも化粧品の「特記表示」ルールとは何か?
化粧品における特定成分の特記表示とは、商品に配合されている成分のうち、特定の成分を広告や包装において表示することを指します。 なお、配合成分の全てを同等に表示する場合は、特記表示には該当しません。
化粧品において特定成分を特記表示することは、あたかもその成分が有効成分であるかのような誤認を生じるおそれがあるため、原則として行わないこととされています。
しかし例外として、以下の条件を満たせば特記表示が認められています。
・化粧品の効能効果の範囲内である「配合目的」を併記すること
・「生薬エキス」、「薬草抽出物」のように成分名称に「薬」の字が含まれるものでないこと
・特定成分が「漢方成分抽出物」のように医薬品という印象を与えるものでないこと
このような前提も踏まえた上で、今回の改正で変更された内容についてご説明します。
「特記表示」に関する定義が変更に
今回の改正の大きなポイントとして、まず「特記表示」の定義が変更となりました。
[旧通知と新通知での違い]
| 旧通知(1985) | 新通知(2025) |
|---|---|
| 商品に配合されている成分中、特に訴求したい成分のみを目立つように表示すること。 | 化粧品における広告や包装において、商品に配合されている成分中、特定の成分を表示すること。 |
つまり、訴求したい成分が強調されているか否かに関わらず、特定の成分を表示することで特記表示に該当することとなりました。
配合目的の表示に関する根拠がより厳格に
さらに今回の改正では、配合目的の表示に関して、根拠に基づいた内容であることが条件として追加されました。
[旧通知と新通知での違い]
| 旧通知(1985) | 新通知(2025) |
|---|---|
| 配合目的は化粧品について効能効果の表現の範囲であって事実であること。 | 配合目的は、化粧品の効能効果及び製剤技術に基づく表現とし、客観的に実証されているものであること。 |
旧通知が制定された時代には想定されていなかったSNSや動画広告など、多様な媒体で成分訴求が行われるようになった現代において、消費者への誤認を防止するために特記表示の規制がより強化されたと考えられます。
表示ルールの主な変更点
ここでは、今回の改正によって具体的にどのように表示ルールが変更されるのかについて、お伝えします。特に重要なポイントは以下の通りです。
配合目的の併記義務化
成分を強調しているか否かにかかわらず、特定の「成分名」だけを記載していた広告やパッケージにおいては、「○○(成分名)△△(配合目的)」のように、配合目的を必ず併記することが必要です。
配合目的は根拠に基づいて表示し、客観的に実証されていることが求められます。今までごくわずかな配合量で配合目的を記載していた場合には削除対応が必要な場合があります。
動画広告における特記表示の明確化
近年増加傾向にある動画広告においては、画面とナレーションで配合目的が容易に理解されるように説明することが明記されました。
具体的には、画面に記載された特記成分の前または後などに配合目的を記載すること、文字の大きさや場所、表示時間などを工夫すること、聞き取りやすい速さで誤認を与えないようなナレーションを入れることなどが対策の一例としてあげられます。
統括的成分の例外削除
「植物成分」「海藻エキス」など、複数の成分をまとめて表現する“統括的成分”については、旧通知では配合目的の記載を省略可能とされていましたが、その例外が今回の改正で削除されました。つまり、今後は統括的成分も個別の成分と同様に配合目的を表示することが必要となります。
医薬部外品の有効成分と重なる成分への表示緩和
ビタミンA・Eなどの医薬部外品の有効成分と重なる成分の特記表示は、従来は誤認を与えやすいことから特記表示は不可とされていました。
しかし、今回の改正により以下の①~③を満たした上で認められることとなります。
① 有効成分であるかのような誤認を与えたり、薬理作用を暗示させたりしないこと
② 化粧品の効能効果の範囲内であること
③ 客観的に実証されたことに基づくこと
適用時期と経過措置:いつから対応が必要?
今回の通知は、発出日である2025年3月10日から適用されます。
そのため、これから新規に作成する表示物から新ルールに適合させていく必要があります。既存の表示物については、廃版予定のものを除き、改版や刷り直し等のタイミングで順次新ルールに適合させましょう。
デジタル広告など修正が容易な媒体については、対応期日などはありませんが可能な限り速やかな対応が求められます。
表示が認められない典型例と代替表現
ここでは、特記表示のNG例と具体的な言い換え表現をご紹介します。
| 例示 | 代替表現の一例 |
|---|---|
| 「プラセンタエキス、コラーゲン配合です」と目立たせずに表記 | 「うるおい成分プラセンタエキス・コラーゲンを配合しています」と表記 |
| 動画広告のナレーションで「アロエエキスを含む化粧水」と言及 | ナレーションで「天然植物保湿成分のアロエエキスを含む化粧水」と言及 |
| 「グリチルリチン酸ジカリウム(消炎剤)配合クリームです」と表記 | 「肌荒れを防ぐ成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合したクリームです」と表記 (広告全体からも有効成分と誤認を与えないよう留意する) |
これらの例を参考に、自社の広告やパッケージにNG例がある場合には修正を行いましょう。
(参考)
・厚生労働省 医薬監麻発0310第3号「化粧品における特定成分の特記表示について」(2025-03-10)
・厚生省薬務局監視課長【参考】化粧品における特定成分の特記表示について(昭和 60 年通知からの変更点)
企業が取るべき対応チェックリスト
今回の改正にスムーズに対応するためには、社内の運用体制を整えることも必要です。ここでは、企業が行うべき具体的な実務チェックリストをまとめました。
社内ガイドラインの改訂を行う
新通知の全文と関連するQ&Aを正確に理解し、社内ガイドラインに反映させます。広告制作の現場だけでなく、法務・コンプライアンス部門、薬事部門、マーケティング部門など、関連部署全体で共有します。
根拠資料を整備する
特記表示を行う成分について、配合目的に基づいた効能効果や製剤技術を裏付ける研究データ・根拠資料を整備します。自社データでも可能とされていますが、第三者性があるかを社内で検討します。
監査プロセスを見直す
広告やパッケージの企画段階から、薬機法や景品表示法などの法令チェックと共に、新通知の特記表示ルールに適合しているかを確認する監査フローを組み込みます。ウェブ静止画や紙媒体だけでなく、動画内のナレーションや画像もチェック対象に含めます。
既存資材を棚卸しする
現在使用しているパッケージや広告物をリストアップし、新ルールに適合しているか棚卸しを行います。廃版予定のものを除き、改版や修正が必要なものを特定します。
広告・薬事担当者は特記表示ルールの改正ポイントを理解し、適切な対応を!
今回の化粧品成分の特記表示ルールの改正は、広告媒体が多様化する現代において、消費者がより理解しやすい表現を求めていることの表れといえるでしょう。
広告担当者は広告やパッケージが新しい基準に適合しているか速やかに現状を分析し、 必要な修正と社内運用の体制強化を進めることが求められます。コンプライアンスを遵守し適切な対応を行うことで、消費者の信頼を得ることに繋がるでしょう。
時間のかかる広告チェックは、AIを活用することで担当者の負担を減らすことができます。広告制作の業務効率化にお悩みの方は、広告チェックAIをぜひご検討ください。
AIを搭載した広告表現チェックツールにURLや画像を入力するだけで、
法令
(薬機法、景表法など)
に抵触しているかどうかを瞬時に確認し、
言い換え文章を出力。
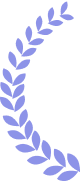
初期費用
0
円
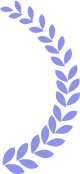
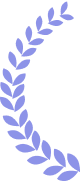
チェック工数
9
割削減
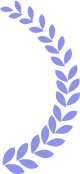
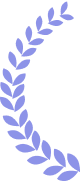
お客様のご要望に応じた
カスタマイズ開発が
対応可能