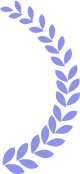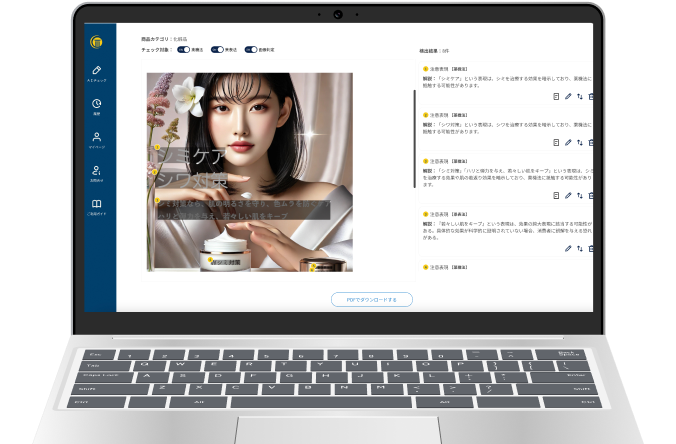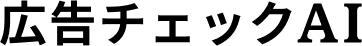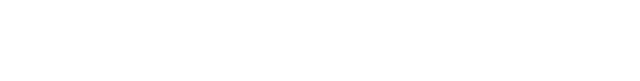BLOG
薬機法における広告の3要件とは?注意すべき媒体やよくあるNG例を解説
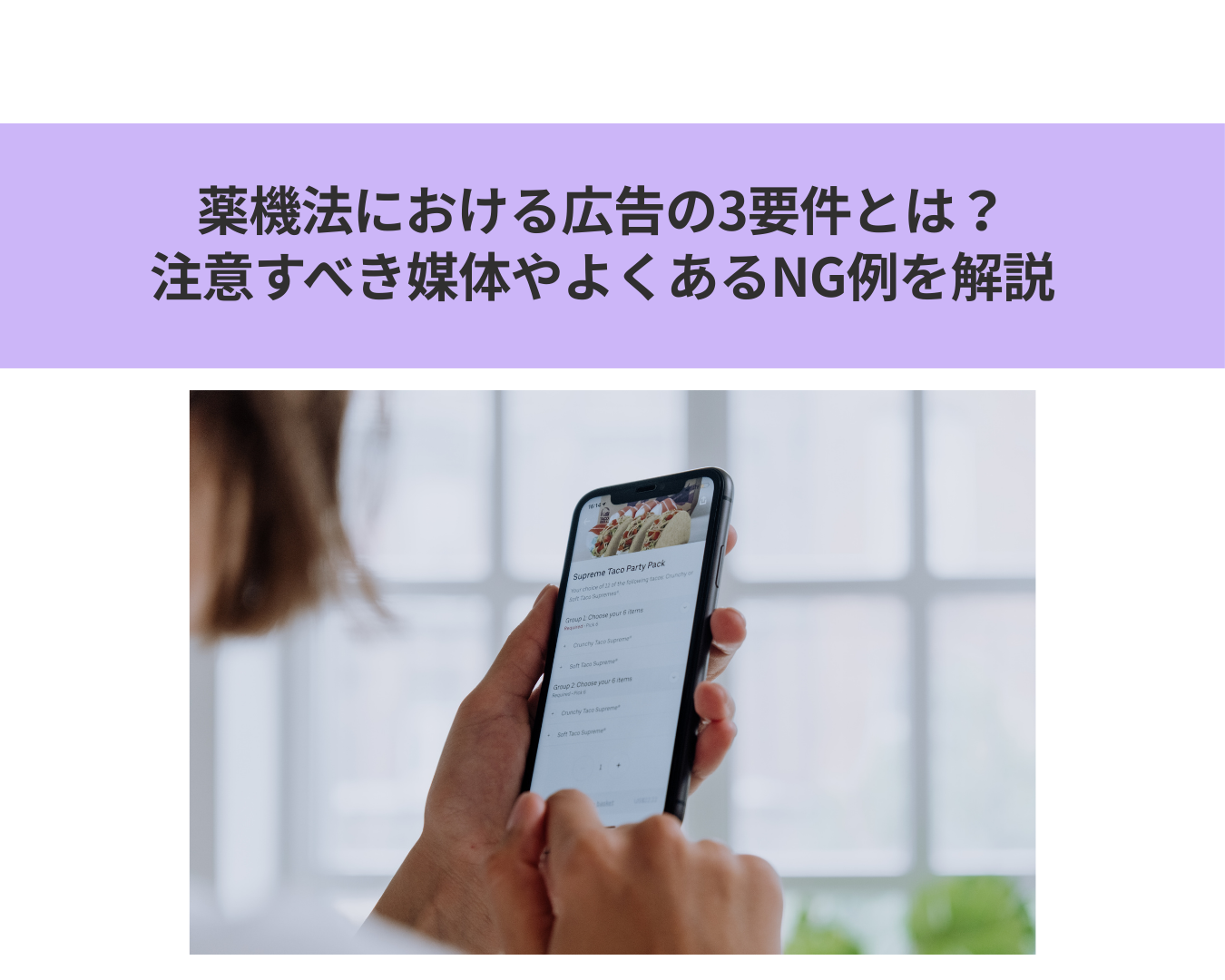
薬機法は、医薬品や化粧品などの品質・有効性・安全性を確保するための法律で、その重要な柱の一つとして広告を規制しています。
では、どのような表現や表示が薬機法の規制対象となる「広告」とみなされるのでしょうか?
その判断基準となるのが「広告の3要件」です。本記事では、事業者や情報発信を行うすべての方が知っておくべきこの3要件を、具体例と共に分かりやすく解説します。
「広告」の判断基準となる3つの要件とは
「これは個人的な感想だから広告ではない」「商品名を明記していないから問題ない」そう思っていても、薬機法上は「広告」とみなされるケースがあります。
厚生労働省は、厚生省医薬安全局監視指導課長通知(平成 10 年 9 月 29 日医薬監第 148 号)により、ある表現物が広告に該当するかどうかを、以下の3つの要件をすべて満たすかどうかで判断することを明記しています。
1.顧客を誘引する意図が明確であること(誘因性)
2.特定の医薬品等の商品名が明らかにされていること(特定性)
3.一般人が認知できる状態であること(認知可能性)
この3つの要件が揃ったとき、その表現は薬機法の規制対象となる「広告」と判断されます。
それぞれについて、順に詳しく見ていきましょう。
要件1)誘因性:顧客を誘引する意図が明確であること
これは、「その情報発信が、顧客の購入意欲を高めることを目的としているか」という点です。
平たく言えば、「この商品を買ってほしい」「このサービスを利用してほしい」という意図があるかどうか、ということです。例えば、「購入ボタン」や「お申込みはこちら」といった案内があったり、割引クーポンや特典がついていたりすると、「誘因性あり」と判断されやすくなります。
【誘引性があると判断されやすい例】
- 商品の効果やメリットを強調するパンフレットやチラシ
- 商品販売ページに誘導する文言があるWEBサイト
- アフィリエイトリンクが貼られたSNS投稿やブログ記事
- テレビやラジオのコマーシャル
【誘引性がないと判断されやすい例】
- 学術論文や学会発表(純粋な研究成果の報告)
- 社内関係者のみに共有される業務連絡資料
- 単なる使用方法の説明書
要件2)特定性:特定の医薬品等の商品名が明らかにされていること
これは、「どの商品のことを指しているのかが分かるか」という点です。
商品名が直接的に記載されていなくても、社会通念上、どの商品についての広告か分かる場合は「特定性あり」と判断されやすくなります。
【特定性があると判断されやすい例】
- 商品名が明記されている広告
- 商品名は書かれていないが、特徴的なパッケージデザイン等や消費者が容易に商品を特定できる表現が掲載されている場合
- 同一サイトで「商品紹介ページ」と「成分の効能効果のみを説明するページ」の両方が掲載されている場合
- 別サイトであるが、「成分の効能効果を発信するサイト」から「商品紹介サイト」への誘導するリンクが貼られている場合
例えば、単に「ビタミンCは美容に良い」といった一般的な情報を発信するだけで、特定の商品に言及していなければ、この要件は満たしません。しかし、そのすぐ下に特定商品の購入リンクがあれば、全体として「特定性あり」と判断される可能性が高まります。
要件3)認知可能性:一般人が認知できる状態であること
これは、「不特定多数の一般人が、その情報を認識できる状態にあるか」という点です。
ここでいう一般人とは、広告を行っている者以外の人々を指します。
現代では非常に多くの媒体がこの「認知可能性」の要件を満たします。
【認知可能性があると判断される媒体の例】
- マス広告: テレビ、ラジオ、新聞、雑誌
- インターネット: Webサイト、ブログ、SNS(X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、TikTokなど)、動画共有サイト(YouTubeなど)、メールマガジン、アフィリエイト広告、リスティング広告
- その他: 電車の中吊り広告、屋外の看板、ポスター、店頭ポップ、配布されるチラシ
特に注意が必要なのが、限定されたコミュニティでの情報発信です。例えば、ログインにIDやパスワード等が必要な会員制サイトであっても、一般人がアクセスできる運用になっていれば、「認知可能性あり」と判断されます。
(参考)
厚生労働省 インターネットによる医薬品等の広告の該当性に関する質疑応答集(Q&A)について
厚生労働省 薬事法における広告規制
3要件を満たすとどうなる?薬機法の広告規制
上記の「誘引性」「特定性」「認知可能性」の3要件をすべて満たす「広告」は、薬機法の規制対象となります。代表的な規制が、薬機法第66条(誇大広告等の禁止)、第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)です。
これらの条文により、例えば以下のような表現を用いた広告は禁止されています。
・事実と異なる、または事実を誇張した表現
NG例:「満足度120%」「絶対に効く」「100%安全」
・医師等が保証しているかのような表現
NG例:「専門医が効果を認めた」「「副作用の心配はない」
・堕胎を暗示したりわいせつな文書・画像を用いた表現
NG例:性的な印象を与える画像の挿入
・承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告
NG例:「米国で承認済み薬〇〇、個人輸入で手に入る」「このサプリでがんが治る」
薬機法では、「何人も」この規制を遵守するように定めており、広告を依頼した事業主はもちろん、広告作成に携わるライターやアフィリエイター、インフルエンサーなども規制の対象となります。
薬機法に違反した場合にはペナルティも
薬機法に違反した場合のペナルティは、行政指導や措置命令に留まりません。悪質なケースでは刑事罰(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)が科されることもあります。
加えて、2021年8月からは課徴金制度が始まり、虚偽・誇大広告の違反で得た売上の4.5%が徴収される可能性も出てきました。
こうした法的な処分を受けると、企業の社会的信用は大きく傷つきます。消費者や取引先からの信頼を失うことは、企業の経営に深刻な打撃になると認識しておくべきです。
(参考)厚生労働省 課徴金制度の導入について
(関連記事)薬機法・景表法入門!初めて広告制作を担当する時の押さえるべきポイントとは?
広告チェックAIを用いて、薬機法を遵守した「広告」制作を!
本記事では、「広告」の判断基準となる3つの要件と、遵守すべき規制についてお伝えしました。
昨今、SNSや動画プラットフォームの普及により、企業が発信した情報はユーザーの手で瞬時に拡散されるようになりました。それに伴い、不適切な広告が広まってしまった際の影響も大きくなったことから、行政による広告規制は年々厳格化しています。
こうした背景から、スピーディーかつ正確なリーガルチェックは、広告ご担当者様にとって喫緊の課題と言えるでしょう。
「広告チェックAI」は、AI技術によって法令違反のリスクを未然に防ぐとともに、広告制作の業務効率化やコスト削減を実現します。
AIによる効率的な広告チェックにご興味をお持ちの方は、ぜひ下記フォームよりお問い合わせください。
AIを搭載した広告表現チェックツールにURLや画像を入力するだけで、
法令
(薬機法、景表法など)
に抵触しているかどうかを瞬時に確認し、
言い換え文章を出力。
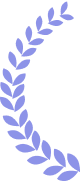
初期費用
0
円
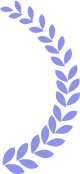
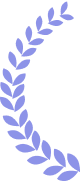
チェック工数
9
割削減
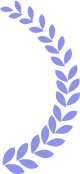
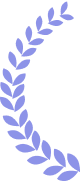
お客様のご要望に応じた
カスタマイズ開発が
対応可能